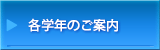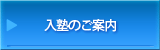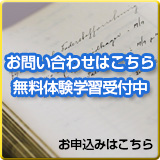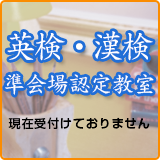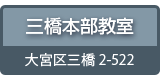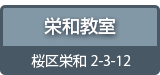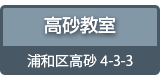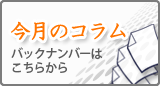- フェニックスアカデミー ホーム>
- 今月のコラム
- バックナンバー>
- 2015/11
今月のコラム 文⁄塾長 大山重憲
味わい
部屋は4畳半と6畳が合計12室。室内にはテレビは無く、2室を除いてバス・トイレも付いていない。畳の上に布団を広げれば部屋いっぱいに。そんな小さな旅館を目指して世界から旅行者が集まってくる。東京下町にある家族経営の日本旅館「澤の屋」(東京・台東区)である。
館主の澤さん(78)は、義理の母が始めた旅館の経営を結婚後、継いだ。東京出張のビジネス客や修学旅行生で繁盛したが、大阪万博(1970年)が終わった頃から様子が変わった。 都心にビジネスホテルが増え、お客さんが流れていった。82年の夏、まさかの宿泊客ゼロが3日連続、慌てて外国人を受け入れていた知り合いの旅館を見学に行ったら満室だった。「うちでもやれるだろうか。日本人が泊まらない旅館に外国人が来るわけない。」悩んだが他に選択肢はなかった。
3年後に稼働率が90%まで上がった。パンフレットを海外に発送し、宿の名前が知られるようになったからだが、もう一つ、下町ならではの伝統があった。周辺は古い寺院や街並みが残る。今年も神社の秋祭りに宿泊客が飛び入り参加した。
江戸風俗研究家の杉浦日向子さんによれば、江戸の長屋には3つのルールがあったという。初めて会った人の生国を聞かない、年齢を聞かない、結婚しているかどうかなど家族のことを詮索しない。いろいろな地方から人が集まって暮らす江戸の知恵だったのだろう。この土壌があるから街も外国人の旅行者を自然に受け入れてくれた。「私も新潟出身のよそ者。下町だからこそ続けてこられたのだと思う。」澤さん自身は言う。
これまでに約90か国・地域から17万人の旅行者を受け入れた。宿泊料は1 部屋5000円台からだが、泊まるのは貧乏旅行の若者だけではない。企業経営者も大学教授もいる。なぜか?「彼らがわざわざうちに来るのは日本の普通の生活を見たいから。だからテレビがないとか部屋が狭いとか苦情はほとんどない。静かでリラックスできると褒められるくらいだ。」
この30年間、試行錯誤しながら勘違いや失敗の連続だった。こんなことがあった。宿泊客に日本の良さを知ってもらおうと、富士山をデザインした布巾をプレゼントした。ところが、チェックアウト後の部屋に入ると、隅に置きっぱなし。腹を立てたり悩んだりしたが、そうかと気付いた。こちらは好意のつもりでも、相手にすれば気に入らないお土産を押し付けられていたのだ。重要なのは文化や習慣の違いを無理やり乗り越えることではなく、違いは違いとして認め、受け入れる。そう腹をくくると世界が広がった。
言葉も勘違いしていた。英語ができず最初は不安で仕方なかった。中学生の息子の教科書を借りて丸暗記した。でも、一番心配していた言葉が一番苦労しなかった。身振り手振りでコミュニケーションはできる。それでだめなら紙に書けばいいのだ。
今や宿泊予約の60%はメールで来るインターネットの時代。それでも澤さんが手書きにこだわるものが2つある。一つは宿の周辺を網羅するA4判の地図。近所に飲食店やATMができると台紙に書き加えコピーを取って宿泊客に渡す。30年前からのスタイルだ。
もう一つは宿泊予約を記入する宿帳だ。予約が入ると鉛筆で書き込みキャンセルは消しゴムで消す。「見てください。来年の桜の季節はもう予約がかなり入っていますよ。」ずっしり重い宿帳は、常連客と旅館の信頼の厚さを物語っているようだった。
「5年後に東京五輪がありますが、増築や建替えは全く考えていません。すべての宿泊施設が同じ方向を目指す必要はない。この先も今のままでいいと思っています。」
自分流を貫く。ぶれない。付和雷同しない。澤さんの職人気質的な頑固さが味わいとなり共感を呼び支持されている。そして下町に溶け込み下町の一部となり、むしろ今や下町の文化を築いているところに誇りとすがすがしさを感じた。